こんにちは!
「テクニカル分析の基礎シリーズ」第4回目は、RSI(相対力指数) を解説します。
シンプルで使いやすく、多くのトレーダーが「買われすぎ・売られすぎ」を判断するのに活用している定番指標です。
RSIとは?
RSI(Relative Strength Index)とは、一定期間の値上がり幅と値下がり幅の比率を計算し、0〜100の数値で表すオシレーター系指標です。
- 70以上:買われすぎ(下落の可能性)
- 30以下:売られすぎ(上昇の可能性)
多くのチャートツールに標準搭載されており、初心者でもすぐ使えます。
👉 関連記事:MACDとは?トレンド転換を見抜く代表的オシレーター
RSIでわかること
- 相場の加熱感
買いが続きすぎているか、売りが続きすぎているかを可視化。 - 反発の可能性
70以上で下落、30以下で上昇のサインとして使われやすい。 - ダイバージェンス(逆行現象)
価格が高値更新しているのにRSIが下がっている → 上昇トレンド弱まり。
価格が安値更新しているのにRSIが上がっている → 下落トレンド弱まり。
RSIのメリット
- シンプルで直感的に理解できる
- 買われすぎ・売られすぎを数値化できる
- ダイバージェンスでトレンド転換のヒントを得られる
RSIのデメリット
- トレンドが強いと「70以上」「30以下」が長期間続くことがある
- 短期のノイズでシグナルが頻発することもある
- 単独で使うとダマシに引っかかりやすい
RSI活用のコツ
- レンジ相場で有効
行き過ぎを狙って逆張りするのに使いやすい。 - トレンド相場では補助的に
強い上昇トレンド中は「30以下にならない」、下降トレンド中は「70以上にならない」ことが多い。 - 他の指標と組み合わせる
移動平均線やサポレジと合わせると信頼性UP。
よくある失敗と対策
- 70以上だから即売り、30以下だから即買い
→ 強いトレンド中は逆に伸び続けるので危険。 - 時間軸を一つだけで判断
→ 上位足と下位足を組み合わせることで精度向上。 - 数値だけに頼る
→ ローソク足やサポレジとセットで確認。
まとめ
- RSIは0〜100の数値で相場の加熱感を測る指標
- 70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎの目安
- レンジ相場での逆張りに有効だが、トレンド相場では補助的に使うのがポイント
- ダイバージェンスを見逃さないようにすることが重要
👉 明日は「ボリンジャーバンド」を解説します!


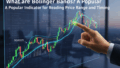
コメント