こんにちは!
「テクニカル分析の基礎シリーズ」第5回目は、ボリンジャーバンド を解説します。
チャートに帯(バンド)を描き、価格の変動範囲を視覚化することで、エントリーや利確の目安を見つけやすくなる人気のインジケーターです。
ボリンジャーバンドとは?
ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に、価格の標準偏差(σ)を加減して描かれる帯状の指標です。
- 中央線:移動平均線
- ±1σ:価格が収まる確率約68%
- ±2σ:価格が収まる確率約95%
- ±3σ:価格が収まる確率約99%
👉 関連記事:RSIとは?買われすぎ・売られすぎを判断する人気オシレーター
ボリンジャーバンドでわかること
- 値動きの幅(ボラティリティ)
バンドが広がる=相場が大きく動いている。
バンドが狭まる=値動きが小さく停滞している。 - 相場のタイミング
バンドが急に広がったときは、トレンド発生のサインになりやすい。 - 逆張りポイント
価格が±2σを大きく超えると、行き過ぎとして反発する可能性がある。
ボリンジャーバンドの活用法
- 順張り
バンドが広がった方向へエントリー。トレンドに乗る戦略。 - 逆張り
価格が±2σ付近で跳ね返る動きを狙う。特にレンジ相場で有効。 - スクイーズ&エクスパンション
バンドが収縮(スクイーズ) → その後の拡大(エクスパンション)で大きな動きが起こりやすい。
ボリンジャーバンドのメリット
- 値動きの「幅」を視覚的に把握できる
- 順張り・逆張りどちらの戦略にも使える
- 他のインジケーターと組み合わせやすい
ボリンジャーバンドのデメリット
- トレンド相場で逆張りすると大きな損失になる
- σの数値設定によって結果が変わる(一般的には±2σ)
- 単独で使うとダマシが多い
活用のコツ
- まずは±2σを基準にする
初心者はシンプルに2σを目安に。 - レンジとトレンドを区別する
レンジでは逆張り、トレンドでは順張りが基本。 - 他の指標と組み合わせる
RSIやMACDと組み合わせると、精度が高まる。
まとめ
- ボリンジャーバンドは価格の変動範囲を示すバンド型インジケーター
- 値動きの幅を把握し、順張り・逆張りの両方に活用できる
- スクイーズからの拡大は大きなチャンス
- 他の指標と組み合わせて使うのがポイント
👉 明日は「サポートとレジスタンス」を解説します!


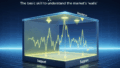
コメント